札幌の弁護士が 相続のお悩みを 親身になって解決します
- JR線札幌駅北口から徒歩2分
- 東豊線・南北線さっぽろ駅徒歩2分
-
来所相談30分無料
-
通話料無料
-
年中無休
-
24時間予約受付
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

来所相談30分無料
通話料無料
年中無休
24時間予約受付
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
北海道は日本の都道府県の中で最も面積が広く、相続の対象となる土地が多く存在します。
また、企業数も多く、遺産相続の問題が発生した際に複雑な問題に発展するケースも少なくないでしょう。
相続対象となるのは財産であることから、相続は「財産の問題」と捉えられることも多いですが、実際には亡くなった方とその周りの方との関係性が大きく影響する「人の問題」であることがほとんどです。相続は法律の専門家である弁護士にお任せください。
以下の記事では、相続の問題全般について解説します。

弊所は多数の相続案件をご依頼いただいております。弊所にご依頼いただくお客様が、弊所のどのような点を評価してくださっているのか、ご説明いたします。
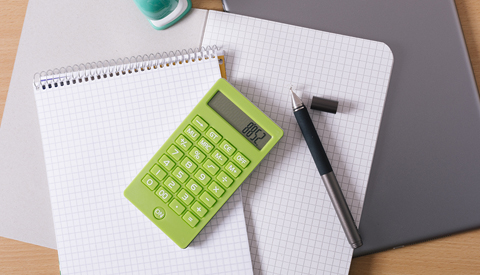
CASE01
当法人は全国に12の拠点を有しており、それぞれの拠点が、それぞれの土地の実情に精通しております。相続問題が発生した際、相続人の方がお住まいの地域と、相続財産が存在する地域が異なることもよくあります。
弊所にご依頼いただきますと、他11拠点と連携してご依頼に対応させていただきますので、地域ごとに異なる風習などにも配慮しながら相続問題を解決することができます。

CASE02
最も良いのは、相続問題を解決することではなく、相続問題を発生させないことではないでしょうか。弊所では、「相続問題を発生させないためにどうすれば良いのか?」といった観点からのご依頼も承っております。
また、相続が発生した後には、遺産の分割だけでなく、故人の生前の生活費の分担に関する交渉なども承っております。遺産分割に限らず、相続に関する様々なお悩みについてご案内させていただきます。
弁護士に相談することで見えてくることはたくさんあるでしょう。相続に迷っている方には、「まずは弁護士法人ALG&Associates札幌法律事務所に相談してみて、後のことはそれから考えよう」と思っていただきたいです。
遺産相続問題が発生した際、ご自身で対応を行うという選択肢もあれば、専門家に相談するという選択肢もあります。遺産を相続人がどのように分けるのか、利害が対立する場面でご依頼を受けられるのは、原則弁護士のみです。
ご自身で対応を行うことに比べ、弁護士に相談・依頼することにはどのようなメリットがあるのか、ご紹介します。
遺産を遺す方から遺される方へ、遺産の分け方についての意思表示を行うことは、最良の贈り物です。
法的には、遺言書で財産の分け方を指定することが非常に重要となります。しかしそれだけでなく、「どのようなことを考えてこの分け方を指定したのか」お伝えすることが、相続問題を防ぐうえで大きな効果を発揮することもあります。
弊所では、ただ遺言書を作成するのみではなく、ご依頼者様がご家族にどのような贈り物をしたいのか伺い、そのご意向が最大限に叶うお手伝いをさせていただきたいと考えています。
遺言書は原則として、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3種類のいずれかの形式で作成する必要があります。
遺言書が効力を発揮する際には遺言書を作成した方が意思表示を行うことができないことから、遺言書が有効となるためには、非常に厳しい形式を守らなければならないことになっています。
また、遺言書を作成しても、相続人が遺言書を見つけられなければ、せっかく作成した遺言書が存在しないことを前提に遺産分割を進められてしまう可能性があります。
どのような遺言書を作成し、どのように残すのかは非常に大切な事柄です。まずは専門家である弁護士へご相談されてからお決めになることをお勧めします。
この度は、ご愁傷さまでした。気持ちの整理がつかないまま、相続問題に対応しなければならない相続人の方のご心労は察しきれないものかと存じます。
なるべく相続人の方のご心労を軽減するべく、ご依頼者様の負担を減らすため尽力させていただきます。
相続問題が発生した際、相続人の方同士で遺産に関する協議を行う場合には、感情的な部分によってなかなか協議が進まないことがあります。
また、本来もらえるはずの財産を見落としてしまい、法律上もらえるはずの遺産よりも少ない遺産しか受け取れないという事態が生じる場合もあります。
弁護士にご依頼いただきますと、弁護士が相続人間での交渉の窓口となり、弁護士が直接やり取りします。ご依頼者様が直接やり取りをする必要はなくなりますから、上記のような事態を避けることができます。
弁護士は法の専門家ですから、法的な根拠に基づいた協議を行うことができます。
法律は無味乾燥なものだと思われることもありますが、これまでに生きた多くの国民の経験や裁判内容をもとに、日本における相続の実情に合わせて改められてきたものです。
また、他の相続人の方が一切譲歩しなかったとしても、法律の定めによりご依頼者様が保証されるべき遺産の取り分については、最終的には裁判所などを使うことで獲得することが可能です。そのため、法的な根拠をもとに協議を進めることで、早期の解決に繋げることができます。
来所法律相談30分無料 相続のお悩みなら私たちにお任せください。
まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします。
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続は、相続財産をお持ちの方が元気な段階から対策を講じることができます。
予め対策を行うことで、残された相続人の方同士の紛争を防ぐことができます。また、相続財産をお持ちの方の希望に沿った遺産の分け方を指定することができます。
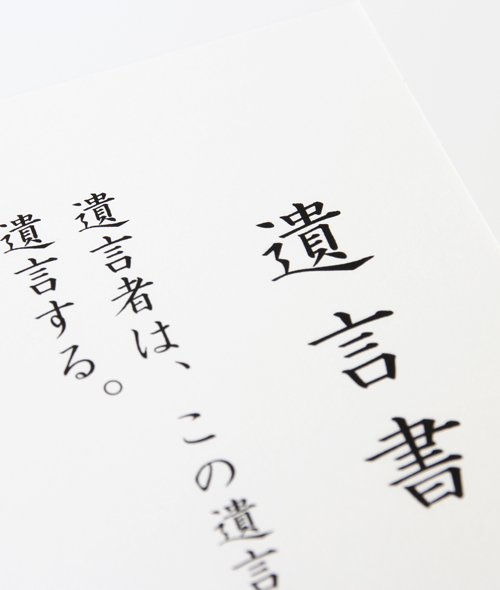
相続の準備01
遺言書を 作成したい
相続問題が発生し、相続人の意向がばらばらな場合、基本的には、遺言書で指定された通りに相続財産を分けることになります。ですから、遺言書には絶大な効力があるといえます。
しかし、そのような絶大な効力がある代わりに、遺言書として作成されたものであっても、法律上定められた要件を満たしていないものは、無効とされてしまい、一切の効力を失ってしまうことがあります。
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類の遺言があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
たとえば、自筆証書遺言では、遺言書の多くの部分を手書きで記載する必要があり、長い文章を書くことが難しい方にとっては、望ましい方式とはいえないでしょう。
弊所にご依頼いただきますと、被相続人の方の健康状態や、財産の価値、相続人間の関係性などを伺った上で、最適な遺言書の種類、保存方法などをご提案させていただきます。

相続の準備02
相続財産を 整理したい
遺言書にて「どの財産を誰に相続させる」と記載するためには、財産の基本的な事項について把握する必要があります。ご自身が一生をかけて築き上げてこられた財産について、全てを詳しく把握されている方は多くありません。
弁護士にご依頼いただくことで、どのような場所にどのような財産があるのか、整理することができます。

相続の準備03
相続税の 対策をしたい
税金の専門家となるのは税理士ですが、弁護士は税理士と連携することで、税金対策に必要な事項を調査することができます。
ご自身が亡くなった場合に法定相続人となるのはどなたなのか、相続対象となる財産はどの程度なのかなど、ご依頼者様からのご要望と許可があれば、弁護士から税理士にご説明させていただきます。
ご相談の際に、「税理士への説明が必要」ということを、お伝えください。
相続が開始した後の流れは、遺言書が存在するかどうかで大きく分かれます。
被相続人の遺言書がある場合には、原則として遺言書に従って遺産を分けることになります。他方、被相続人の遺言書がない場合には、相続人間で遺産分割協議等を行うことになります。
遺産分割協議がまとまらなかった場合には、遺産分割調停や遺産相続審判といった、裁判所を使う手続きに移行します。また、遺言書の有無にかかわらず、相続人の調査・相続財産の調査を行うことが必要です。
被相続人の方が亡くなった後、最初に確認するべきことは、遺言書が存在するかどうかを確かめることです。
しかし、遺言書が見つかったとしても、安易に封筒を開けてはいけません。
自筆証書遺言の場合、封筒を開ける前に裁判所にて「検認手続」という手続きを行わなければならないことになっています。
そのため、被相続人のご自宅で自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見したとしても、ご自身で開封せず、弁護士にご相談ください。
また、「遺言書」と記載されている書面が見つかったとしても、法律上の要件を満たしていない場合には、有効な遺言書として扱われない可能性があります。有効な遺言書が存在するかどうかについては、慎重に判断を行う必要があります。
遺言書が存在しない場合、相続人同士で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を行うこととなります。
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならず、相続人の誰かが欠けた状態で行った遺産分割協議は無効となってしまいます。そのため、誰が相続人なのか、調査を行う必要があります。
相続人の全員を明らかにするためには、被相続人の戸籍を取得して戸籍から調査することになります。
戸籍には配偶者の有無や子の有無などが記載されています。
本籍地を変更すると戸籍は新しく作られ、以前の戸籍に記載されている内容は基本的に新しい戸籍には引き継がれません。
そのため、相続人を明らかにするためには、被相続人がこれまで本籍地を置いた全ての場所の戸籍を取り寄せる必要があります。
被相続人の戸籍の内容次第では、更なる調査を行わなければならない可能性もあります。
なお、相続人の全員を明らかにする資料は、遺産分割協議の場面だけでなく、遺産分割協議が終わった後に分けられた財産を移動させる際にも必要になります。
遺産分割をするためには、被相続人の遺産の種類や金額を正確に把握する必要があります。
遺産分割を行った後に分割未了の遺産が判明しては、困ってしまいますね。
遺言書がある場合でも、遺言書に記載のない遺産が存在する場合には、相続人の間で協議を行わなければなりません。そのため、相続財産の調査が必要となります。
調査する対象としては、預金口座や証券口座、不動産等があります。
相続には、単純承認、限定承認、相続放棄という方法があります。
単純承認とは、被相続人のプラス及びマイナスの財産の全てを引き継ぐという方法です。最も一般的な相続の方法にあたります。
限定承認とは、被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。
相続放棄とは、被相続人のプラス及びマイナスの財産の全てを相続せずに放棄するという方法です。つまり、相続をしないということですね。
限定承認もしくは相続放棄は、原則、相続が開始したことを知ってから3か月以内に決断しなければなりません。
3ヶ月経過前でも、相続財産の処分など、一定の行為をしてしまうと、単純承認をしたとみなされてしまうので、注意が必要です。
相続税は、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合に発生します。
基礎控除額は、3000万円+(600万円×相続人の人数)で計算できます。養子がいるような場合では、基礎控除の計算が変わることもあります。
相続税は、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告した上で、納税しなければなりません。
10ヶ月という期間は、遺産分割協議を行う場合、かなり短く感じられると思います。
相続税の申告期限までに遺産分割が完了しない場合には、ひとまず法定相続分に従った相続税を申告して支払い、後から修正等の対応を行うことになります。
Case01
被相続人が遺言書を作成していた場合、原則として、遺言書に記載された内容の通りに相続が行われます。
相続財産は元々被相続人のものですから、相続財産を分ける際には被相続人の意思が尊重されるべきだと考えられているのです。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、被相続人の自宅などに保管されていることがあります。
相続人や利害関係者が遺言書を改ざんすることを防ぐため、遺言書が入った封筒を見つかった場合、その場で開封してはならないことになっています。
法律上、勝手に遺言書を開封する行為は、5万円以下の過料の支払いを命じられることもある行為ですし、相続人間での争いを誘発してしまうことにも繋がりますので、絶対に行わないでください。
遺言書が見つかった場合には、裁判所で検認手続という手続きを行います。検認手続のなかで封筒が開けられ、遺言書の内容を確かめられるようになります。
検認手続は検認手続当日の遺言書の内容を明確にするための手続きですので、検認手続が行われたからといって、遺言書が必ず有効なものと認められるわけではありません。
遺言書に無効事由がある場合には、別途遺言書の無効を主張していく必要があります。
遺言執行者は、遺言者に代わって、遺言者が作成した遺言の内容を実現する役割を負う方です。
遺言を遺した方は、遺言の効力が発生する際には既に亡くなっています。
そのため、遺言を実行するために誰かが積極的に動かなければならないような場合など、遺言執行者が定められる場合があります。
遺言執行者は、被相続人が遺言書の中で指定している場合もありますし、遺言執行者が必要な相続のケースなどで、相続人が家庭裁判所に申し立てることによって選任される場合もあります。
遺言執行者は、遺言内容を実現するために、遺産の管理や遺産の名義変更、寄付など、様々な行為を行うことが出来ます。
Case02
被相続人の遺言書がない場合、相続人間で相談して遺産の分け方を決めることになります。
遺産の分け方を決める話し合いのことを、遺産分割協議といいます。
協議で話し合いがまとまらないような場合には、遺産分割調停や審判といった、裁判所を用いた手続きの中で遺産の分け方を決めることになります。
遺産の分け方が決まったら、相続人全員が協議した内容を書面に記載し、署名や押印などを行って、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書を示すことで、被相続人名義の預金口座からお金を引き出したり、被相続人名義の不動産の名義変更を行うことができます。
たとえば、亡くなる直前まで元気だった方が被相続人で、遺産が預貯金しか存在しないような場合、相続人が同じ割合で預貯金を分割するということで協議がすぐにまとまるケースがあります。
しかし、被相続人が長い間介護を必要とする状態で、特定の相続人だけが介護を負担してきたようなケースや、被相続人が特定の相続人だけに対して多額の贈与を行っていたようなケース、被相続人が不動産を有しており、その価値について相続人の判断が分かれるようなケースでは、なかなか協議がまとまらないことも多いです。
そのような場合には特に、法的な原則論を示す必要があります。
Case04
法定相続人であっても、遺産を必ず相続しなければならないわけではありません。
借金など、被相続人の負の遺産が多い場合や、被相続人が有する不動産が引き取り手の見つからなさそうなものである場合など、相続人が相続を希望しない場合もあるでしょう。
そのような場合、相続放棄という手続きを行うことが可能です。
被相続人の有するプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続をすることによって経済的に損をしてしまうことになります。
ですから、相続放棄をするかどうか決めるため、被相続人有する負債がどの程度の金額なのか調べたいという方は多くいらっしゃいます。
弊所では、信用情報機関に問い合わせたり、被相続人の金融機関取引履歴を取得するなどして、被相続人の負債を調べるお手伝いをさせていただいています。
相続放棄をすべきか悩んでらっしゃる方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
相続放棄を行った場合でも取得できる財産が存在する場合があります。
弁護士にご相談いただければ、ご依頼者様が相続放棄を行った場合のメリットやデメリットなどを、ご依頼者様のご事情に即して具体的にお伝えすることが出来ます。
被相続人が負債を残して亡くなってしまった場合、債権者から相続人に連絡が来ることがあります。
債権者は相続人に債務を相続してもらい、債務を返済してもらいたいと思っています。
そのため、債権者は、相続人が相続放棄できない状態にするため、様々な交渉を行ってきます。
法律には、「単純承認したとみなされる」行動が定められていますので、うっかりそのような行為を行ってしまうと、相続人が相続放棄できなくなってしまうことがあります。
弁護士であれば、債権者へのご連絡も承ることができますので、債権者からの連絡にお困りの方は、ぜひ弊所へご相談ください。
遺言書が存在するけれど、納得いかない。相続人間で遺産分割協議を行っても、話し合いがまとまらない。
相続については様々なお困りごとがあるかと思います。
お悩みごとに、どのような解決法が可能なのか、ご案内いたします。

相続問題では、これまでの長い関わり合いの中で形成された感情的なもつれが影響し、相続人間でもめてしまい、結論が出ないことも少なくありません。
そのような場合、まずは、法律上妥当な分け方を検討し、その分け方で全員が納得できるのか、判断を行います。
法律上妥当な分け方では納得いかない人がいるような場合、話し合いでの解決は難しいでしょう。
遺産分割調停や遺産分割審判という、裁判所で行う手続きに移行し、遺産分割について裁判所の判断を仰ぐことが、早期解決に繋がると思われます。

被相続人が有効な遺言書を作成し、遺産の分け方を指定している場合は、原則遺言書のとおりに遺産を分けることになります。
しかし、あまりにも一部の相続人が取得できる財産が少なく不平等な場合、遺留分侵害額請求という請求を行うことができます。
遺留分は多くの場合、法定相続分の2分の1となります。まずは、ご自身の取り分が遺留分を下回っていないか、確認してみましょう。
なお、被相続人の親が相続人に含まれている場合など、遺留分の計算が異なるケースもあります。

生前贈与を受けた相続人がいる場合、生前贈与の金額を遺産に加えた上で分割を行うべきケースがあります。
生前贈与の金額を遺産に加えることを、「持ち戻し」と言います。
持ち戻しを行うかどうかは、生前贈与の内容、性質や金額、被相続人がどのような意思表示を行っていたかどうかなどを考慮して決められます。
また、生前贈与の金額をどう判断するかにあたっては、被相続人の生活水準なども影響します。
これらのことを考慮した上で、持ち戻しを行うべき場合には、生前贈与の金額を遺産に加えた上で遺産分割を行い、生前贈与を受けた人が取得する財産は、生前贈与を受けた金額分控除されることになります。

相続人が、被相続人が経営している会社を手伝ったり、被相続人の介護などを担当した場合、その相続人が取得する相続財産が増額されるべきだと判断されるケースがあります。
相続人の行為によって、被相続人の遺産が減らなかったり、増額したといえる場合には、その利益は相続人に帰属させるべきだと考えられているのです。
このように、相続人が被相続人の財産に対する貢献を行った場合に、その相続人が他の相続人よりも多く遺産を受け取れる制度のことを、寄与分といいます。
他の相続人が寄与分の金額について納得し、寄与分があることに基づいた遺産の分け方に応じてくれるような場合には、話し合いで解決することができるでしょう。
しかし、寄与分については、費やした労力の捉え方などが分かれ、なかなか相続人全員が納得できることは少なく、話し合いが難航することがほとんどです。
そのような場合には、調停や審判といった裁判所を用いた手続きを利用することも検討すべきでしょう。

被相続人の遺産の中に不動産が存在する場合、揉めてしまうきっかけとなることがあります。
不動産は、相続人のうちの一人が全て取得することも可能ですが、相続人全員で共有することも可能ですし、売却した上で得られた金銭を相続人間で分配することも可能です。
不動産に思い入れのある相続人が多いようなケースでは、誰が不動産を取得するのか、決まらない場合もあります。
また、相続人のうちの一人が不動産を全て取得するような場合、他にめぼしい財産がないのであれば、不動産を取得した相続人は、不動産を取得しなかった相続人に対し、不動産取得の代償として金銭を支払う必要があります。
代償として支払う金銭の金額を決める際、不動産の価値がいくらであることを前提にするのか、揉める場合があります。
その際には査定などをとり、客観的資料をもとに不動産の価値を算出して交渉を行う必要があります。
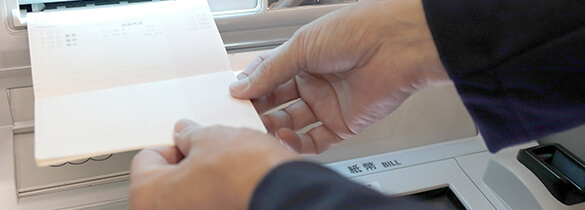
被相続人が生前高齢で認知症であったような場合で、相続が開始してから財産を調べていると、預金通帳に高額の出金履歴が記載されていた、というようなケースがあります。
引き出されたお金が被相続人の施設費用などに費消されていれば良いのですが、使い道が不明な場合も少なくありません。
被相続人がお金を引き出したり、自分のために使ったりできない状態なのに引き出されてしまったお金は、引き出した人が勝手に使い込んでしまっている可能性があります。
そのような場合、使い込んだ人に対して、使い込んだお金を返還するように請求を行うことが考えられます。
使い込んだ人が相続人ではないような場合、問題の解決方法は遺産分割に留まらず、民事訴訟を起こすべき場合もあります。
まずはご事情を弁護士にお伝えいただき、ご相談ください。
まずはお電話やWebページのフォームなどから、弊所へご連絡ください。
弊所で相続を中心に担当しているスタッフがお客様の問題やご要望を伺い、お客様がご来所可能な日程で、法律相談の設定をさせていただきます。
その後、お客様の問題を解決するために適切な弁護士が担当となり、お客様のご事情を詳細にお聞きして、どのような解決方法が可能か、ご提案させていただきます。
ご納得いただけましたら、問題解決を弊所にご依頼ください。
01
お問い合わせ
02
ご予約
03
来所相談
04
ご契約
05
解決
来所法律相談30分無料 相続のお悩みなら私たちにお任せください。
まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします。
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

ご自身が亡くなった後の相続の準備をしたいと考えてらっしゃる方には、相続問題を未然に防ぐために尽力させていただきます。
一度相続問題が発生してこじれてしまうと、それまで仲が良かったご兄弟が疎遠になってしまうというケースも多くあります。
相続問題が起こらないように準備をすることは、人生の締めくくりにふさわしい、遺された方へのプレゼントだと考えています。
既に起こってしまった相続問題の対応に悩んでらっしゃる方には、なるべく相続問題が納得できる形で早期に解決できるよう、尽力させていただきます。
ご自身が得られるべき財産は取得したいと考えられる一方で、相続人同士の関係性が壊れてしまうことは避けたいという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
ご本人で直接交渉していると、言うつもりでなかったことまで言ってしまい、関係性がこじれてしまうことがあります。
弁護士を間に入れていただくことで、直接やり取りをしなくて良くなりますから、ご依頼者様が冷静になって考えやすくなります。
また、弁護士から、法律やこれまでの判例などがどのような考え方を示しているのかなど、ご依頼者様が納得して話し合いを進められるようなご説明をさせていただきます。
近年、札幌には北海道全域から移住される高齢者の方が増えているとのことです。
被相続人の方が最後に住んでいた地域が札幌であれば、遺産分割調停・審判は、札幌の裁判所が管轄となります。
また、相続人の方が札幌にお住まいであれば、札幌の法律事務所にご相談いただくのが最適でしょう。被相続人の方が最後に住んでいたのが札幌でなくとも、弊所でご相談・ご依頼をお受けすることが可能です。
当法人には全国12ヶ所の拠点がありますから、地域によって異なる風習に対応し、事件解決までサポートさせていただきます。
相続についてお困りの際には、ぜひ、弊所へご相談ください。
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※30分以降は、30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談となります。
※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。
※当日、当法人にご依頼いただきました場合、延長された法律相談は無料とさせていただきます。
延長をご希望された場合でも他のご予約の関係で対応できないケースもございますのでご了承下さいませ。